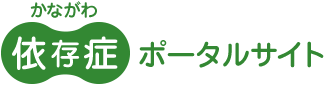神奈川県立精神医療センター依存症診療科の3つの特徴
掲載日:2025年04月24日
投稿者:神奈川県立精神医療センター
神奈川県立精神医療センター 依存症診療科コメディカル部長 青山 久美
神奈川県立精神医療センター依存症診療科は1963年に開設されたせりがや病院(旧せりがや園)として産声を上げ、長い歴史をかけて依存症の治療文化を築いてきました。2014年には芹香病院と合併し神奈川県立精神医療センター依存症科として生まれ変わり、その後も時代の変化に合わせて進化し続けています。このコラムでは、当科の3つの特徴をご紹介します。
1)あらゆる依存症に対応します
2)人に頼り、依存対象に頼らなくて済むようになることを目指します
3)多職種で、地域と連携しながら治療します
1)あらゆる依存症に対応します
依存症にはアルコール、覚せい剤、市販薬、処方薬、大麻といった物質の依存、ギャンブル、ゲーム、盗癖といった行動の依存、性依存などの関係の依存と、様々な依存対象があります。当院は全国に治療施設の少ない薬物依存症治療を担ってきた歴史があり、全国に先駆けてSMARPP(スマープ:せりがや覚せい剤再乱用防止プログラム)を始めるなど、薬物依存症の患者さんを積極的に治療してきました。近年は社会の変化に伴い患者さんの依存対象も変化していますが、依存対象を問わず回復のお手伝いをしています。多様化する依存症に対応するため、以前から実施しているアルコールや薬物のプログラム(SARPP:サープ、SMARPP:スマープ)に加え、2023年にはGRIP(グリップ:ギャンブル依存症のプログラム)をこいプロ(行動の依存症のためのプログラム)に変更し、ゲームや買い物などギャンブル以外の行動の依存症にプログラムを提供できるようになりました。また、同年には性的マイノリティである方のための依存症外来(レインボー外来)を開設し、様々な背景に配慮した治療を展開しています。さらに、思春期診療科と依存症診療科の二つを備えた当院ならではの外来として、2020年に思春期ゲーム行動症外来を開設し、ゲームの問題で困っている中高生の治療に当たっています。
2)人に頼り、依存対象に頼らなくて済むようになることを目指します
依存症だけでなく、その背景にある逆境体験や精神科合併症、発達障害特性などを分析し、お一人お一人にあった治療を考えます。依存対象を無理やり引き離しても回復したとは言えません。自分の感情に気づけない、人を信頼できないといった課題や、依存対象に頼って生き延びてきた歴史を紐解くことで、依存対象が必要なくなることを目指します。感情に気づき、人に伝えることが難しい患者さんのために、感情とコミュニケーションのためのプログラム(SCOP:スコップ)をご提案することもあります。治療を通してその人が依存対象ではなく人を適切に頼り、安心して生きていけるための方法を一緒に考えていきます。
3)多職種で、地域と連携しながら治療します
依存症は偏見にさらされることが多いため、人に言えず長い間悩んだ末にようやく受診される患者さんは少なくありません。当院では、医師、看護師、心理士、精神保健福祉士等様々なスタッフが治療に参加し、皆さんが安心して話せる場を提供しています。また、地域の自助グループや回復施設を紹介したり行政や福祉と連携したりしながら、患者さんやご家族が人とのつながりを回復するお手伝いをします。
依存症に悩む患者さんお一人お一人が地域で安心して過ごすことができるよう職員一同尽力してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。